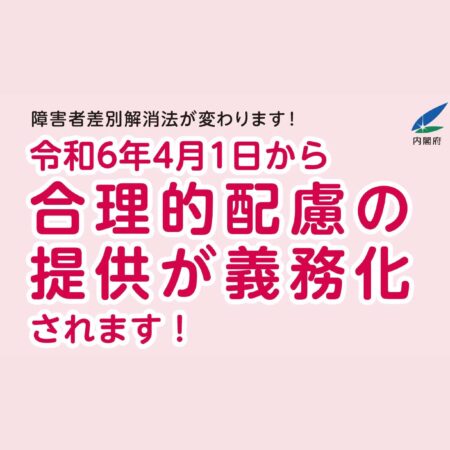夏の風物詩の松戸市の花火大会そして、伝統行事のもち投げを開催予定!
みなさんこんにちは、木村です。
8月に入り各地で花火大会など、夏を彩る風物詩で賑わっています。
ここ松戸でも一昨日、松戸市の花火大会が開催されました。
こちらの動画は江戸川の土手から見た松戸の花火大会の様子です。
この日は、市川市、板橋市、柏市手賀沼その他数カ所で、いろいろな花火大会が開催されておりました。
前日の台風接近で心配でしたが、少し風が強かったものの各地で無事に開催されたようです。
このような花火大会は、夏の風物詩ですが、弊社では少し変わった伝統的な行事を近々行う予定です。
それは、「もち投げ(餅投げ)」という、日本の伝統的な行事で、お祝いごとの場面で餅を投げて配る風習です。

地域によっては「餅まき」とも呼ばれるものですね。
多くは「祝い事」の際に行われることが多いです。
例えば、
1)上棟式(じょうとうしき):家を建てる際、棟が上がったことを祝う
2)地鎮祭(じちんさい)
3)寺や神社の祭り
をはじめ、今ではほとんど見られませんが、時には、成人式や結婚式、地域のお祭り(縁日など)でも見られた日本の伝統行事です。
高い場所(建物の2階や足場、やぐらなど)から、餅やお菓子、小銭などを下に向かって投げ、下で待つ人々は、袋を持ってキャッチしたり、拾ったりします。
餅は紅白餅が定番で、個包装されたものや、ケガ防止のための柔らかい餅が使われることもあります。
今では、小銭はなかなか見かけないですが、昔は時には小銭を小さな封筒に入れて投げられたりしておりました。
この行事本来の意味は、厄払い・福を分けるという意味があり、「福餅」とも呼ばれることがあります。
このように投げることで、福を広く周囲の人に分け与えるという縁起担ぎの儀式です。
そして今回弊社で行う、上棟式での餅まきは、災いを祓うための「散餅銭の儀」がもとになっているといわれています。
家を建てることは大きな厄災を招くという考えがあり、その厄を避けるために餅や小銭をまいて、人々に幸せを分け与えたことが始まりとされています。
また、家を建てることは富の象徴であり、その富を地域社会で分けることで、共同体の中での生活を円滑にするための習慣だったようです。
餅は神様への供え物であり、それを分け与わることで神聖な力が授かり、健康になれるという意味合いもありました。
このもち投げを通して近隣住民との親睦を深める良い機会になり、さらに工事関係者への感謝の気持ちを表すこの伝統行事を、来月ここ松戸新田にて行う予定です。
正式な場所や日時はまた、決まり次第、このWEBサイトでもお知らせ致します。
皆様、暑い日が続きますので、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。
木村でした。
【追記】8月21日 日時が決定しましたのでお知らせします。